
子どもたちに救命を伝える「救命教育」
- 2025-3-27
- 取り組み
- #高度救命救急センター, #救命教育, #救命学習, #救急救命士
2024年4月に、より高度な救急医療を提供する施設となった当院の「高度救命救急センター」。センターでの救急医療はもちろんのこと、津市を中心とした地域の救急医療体制の強化や災害医療の整備などにもさらに力を注いでいます。
そして、その幅広い院外活動の中に、子どもたちを対象とした「救命教育」という取り組みがあります。「子どもたちに救命の意味や手法を教えるのは早すぎるのでは?」という素朴な疑問への答えが、救命教育に関わってきた伊藤亜紗実医師と富田泰成救急救命士の話の中にちりばめられていました。
それいけ!三重大学病院。それ行け!救命教育。みんなで助け合う「救命の連鎖」を育てるために。
| 高度救命救急センター 助教/研究医長 |
|---|
| 救急科専門医 伊藤 亜紗実 |

| 鈴鹿医療科学大学 講師 三重大学病院ハイブリッドワークステーション第1期メンバー |
|---|
| 救急救命士 富田泰成さん |
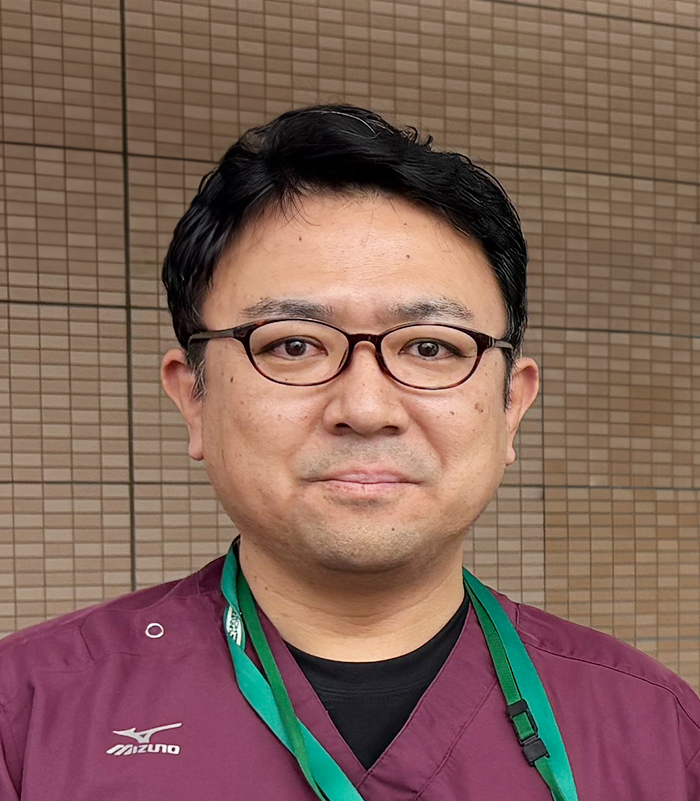
「救命教育」は、どのような主旨で始まったものなのですか。
伊藤: 総務省「令和4年版救急救助の現況」によると、119番通報してから救急車が到着するまでに全国平均で9.4分かかると報告されています。心肺停止で倒れた場合では、その間に、現場にいた人による蘇生処置が行われたかどうかによって救命率は大きく変わります。
突然死で亡くなる方を減らすには、誰かが倒れた時にその場ですぐ適切な救命処置ができる人をいかに増やせるか、つまりは社会における救命講習の普及がとても重要です。私たちはその一環として、子どもたちへの救命教育を始めました。
実は、2011年にさいたま市内の小学校の生徒が突然死で亡くなるという痛ましい事故がありました。この事故を教訓として、その生徒さんの名前(明日香さん)をつけた教職員用事故対応マニュアル「ASUKAモデル」ができ、教育現場に普及しました。
それだけでなく、子どもたちにも救命の連鎖(傷病者の救命から社会復帰に導くのに必要な一連の行動)やAEDを知ってもらうことで学校内での安全が高まり、明日香さんのような事例を繰り返さないことにつながるとして、国内では救命教育が広がってきたという背景があります。

子どもたちに学んでもらうことが、社会における救命への意識を高めるのでしょうか。
富田: 私たちの取り組みは、「命を守る」という最も重要な教育を初等教育の段階から子どもたちと一緒に学び、考えたいという思いから始まりました。
子どものころから学ぶことで記憶が定着し、中学、高校と教育を繰り返すことで、より効果的な教育につながると考えたからです。
伊藤: そして、子どもたちへの救命教育の大きな利点は、知的好奇心の高い時期に教えることができること、そして、親など周りの大人への普及効果も期待できることにあります。
さらに、学校教育の中で行うことができれば、社会的背景に関わらず平等に心肺蘇生法を普及させることができるという利点もあります。
三重県でこの救命教育を始めたきっかけは、子どもたちに楽しく救命処置を教える「子どもメディカルラリー」というイベントが大阪府の千里救命救急センターで行われており、県内でも開催したいと思い始めたことでした。
そこから次第に人の輪が広がり、学校の先生や学校内でお子様を亡くされたご遺族の方と知り合うことになり、次第に活動が広がってきました。

具体的にはどういった構成になっているのですか。
伊藤: 私たちの行なっている救命教育は、3段構成となっています。
1つ目は、オンライン学習教材である「きゅうめいノート」です。心肺蘇生法を動画やクイズとともにわかりやすく紹介し、誰でも見られるようになっています。
2段目が、小学校で学校の先生と行う救命教育の授業で、三重大学附属小学校の教諭が内容を立案してくださっています。
1時間目には、校内にAEDがあったのにも関わらず亡くなってしまった明日香さんの事例について学び、その時どうしたらよかったのか考えるきっかけを作ります。続けて具体的な心肺蘇生法についての座学で、医療従事者による心臓模型を使った説明などを通じて、子どもたちの学びを深めます。
2段目の最終は、実際にペットボトルや人形を使って体を動かしながら胸骨圧迫(心臓マッサージ)を学ぶ実技です。

小学校高学年でも、体型や体力的にこれを的確に行うのが難しい子も多いのですが、ここでは数値目標(深さ約5センチで6センチを超えない、速さ100~120回)を達成することは目的としていません。声を掛け合って救命の連鎖を止めないことを意識しています。
3段目は、子どもメディカルラリーです。チームを作り、これまでに得た知識とスキルを用意したシナリオの中で実践できるかどうかにチャレンジします。
このメディカルラリーは、医学部の5年生が運営しています。病院実習で大変な中、毎年様々な工夫をして完成度の高いイベントを作ってくれています。
子どもメディカルラリーの参加者の中には、数年連続で参加してくださる方、希望して年長さんから参加してくださる方などもいます。
1から2段目までの授業は、附属小学校とオンラインでつないだいくつかの小学校に限って行っていますが、とても意義深い授業なので県内各地の小学校にもっと広がるといいなと思っています。

万が一の場面で判断し、救命活動を行うことは、小学生にはなかなかのチャレンジだと思うのですが、救命の意味や手法を教えるのは早すぎるというわけでないのですか。
伊藤: 実は、ある論文には、4歳の子どもにも救命の連鎖を教えることができると書かれています。また、「KIDS SAVE LIVES」という子どもたちに救命教育を広げるキャンペーンが、WHO推奨のもと欧米を中心に10年ほど前から展開されています。
実際に、日本各地でも子どもたちが心肺蘇生法を行い、救命に至った報告は数々挙げられています。10歳頃であれば心肺蘇生法と救命の連鎖を実践することは十分に可能です。
一般の方々に知っていただきたい救命措置にもいろいろなレベルのものがありますが、前提として、子どもの年齢と発達に応じた救命教育を行うことが重要です。高校卒業までの救命教育の有用性がほぼ確立された今、今後は具体的な方法の検討がされていくと思います。
子どもたちにもできることがたくさんあるということなのでしょうか。
伊藤: その通りです。小学生のうちに普及員や救命士並みに心肺蘇生を行えるようにすることが目標ではありません。
例えば、人を呼ぶ、救急車を呼ぶ、というのも立派な救命活動です。そして、小学校の全児童がAEDは何で、どこにあるのかを知っていることが理想だと思いますし、誰でも目につくような場所に設置することも大事です。
先ほどご紹介した明日香さんの事例では、養護教諭を呼びに行くことに時間を取られてしまったことが後の検証で明らかになりました。基礎的心肺蘇生法を行うことに資格はいらず、誰でもできるという知識、誰か1人が助けるのではなくてみんなで助け合うという意識、それが安全な学校や社会につながるんだということへの理解と共有、こういったものが子どもたちへの救命教育では重要なポイントだと思います。

子どもたちも学校や社会の救命を支える一員なんですね。
富田: 救命教育では、初等教育に医療従事者が参画し、救命に関する授業を行っています。「どうすれば心肺停止の人を助けることができるのか」を考えるところから始まり、心肺蘇生法の理論や実技まで教育してもらっています。
この救命教育を始めたときには、どうなるか分からない不安もありましたが、第一回目から子どもたちは想像を遥かに超える力を発揮してくれました。今では子どもたちの力を100%信じています。
私は、この教育を通して、子どもたちには「よく考え、行動できる人」を目指して欲しいと思っています。
2024年度は2月7日に公開授業が行われました。どんな様子でしたか。
富田: 今回は、日本AED財団 第7回schoolフォーラムの第1部として、救命教育の公開授業が行われました。
授業には、三重大学教育学部附属小学校5年A組の児童32名が対面式の授業に参加しました。その他、同校の5年B組、5年C組の児童、四日市市の日永小学校、常盤小学校、県小学校、松阪市の黒部小学校、中原小学校、柿野小学校、宮前小学校から5年生がオンラインで参加してくれました。
私は対面授業に参加をしたのですが、とても印象深いことがいくつかありました。
その一つが、心臓マッサージを行うときの胸骨圧迫の質を考える場面で、あるグループが「5㎝押さなければいけないけど、6㎝以上押すと骨とか臓器が壊れると思う」と子どもたち同士で討論していました。メリットだけでなくデメリットまで、子どもたち自ら討論していたことにとても感銘を受けました。

まさに「よく考え、行動できる人」としての一歩が踏み出されていますね。
伊藤: 私自身は遠隔で参加しましたので、ビデオ越しで現場の様子を拝見していたのですが、心肺蘇生法の授業の時に、すべての小学校でたくさん手が上がっている様子が見え、活発に発言している姿が印象的でした。
また、附属小学校の児童がポスター発表を行ったのですが、まるで学会会場のような堂々とした発表姿に感銘を受けました。質疑応答も大変印象に残りました。
同日開催のシンポジウムでは、学校関係者、消防関係者、医療に関わられた立場、それぞれから現場で問題視されていることについてご発言いただき、私自身も大変勉強になりました。
例えば、地域住民も使えるようにAEDを校門に取り付けている学校が紹介され、その問題点やハードルなどが取り上げられました。
このように教育、医療、消防が集まる場というのは、私が知りうる限りではこれまでになかったと思います。立場により課題もそれぞれであるにせよ、同じ思いを持ち、同じ方向を向いていると感じました。

この救命教育を今後はどのように発展させていきたいですか。
伊藤: 教育学部学部長挨拶で伊藤信成先生が教育学部の学生へのBLS (Basic Life Support:一次救命)に関する講習を開始されたとお話しされていました。このような形でも救命教育が広がっていることを非常に頼もしく感じました。
地域医療を担う大学病院としては、今後も学校関係者や消防関係者と協力しながら、地域全体の安全性を向上させるための課題を明らかにし、その解決策を模索したいと考えています。
また、三重県内には、各所に救命教育や心肺蘇生法普及に尽力されている方がいらっしゃいますので、他の地域とも連携し、互いにノウハウを教え合って、全国でもバイスタンダー率(救急車到着までの間に一般の人が心肺蘇生など応急措置を行う割合)の高い県にしていきたいです。
それから「きゅうめいノート」は、大人も参考にできる内容です。ぜひご参照ください。
富田: 冒頭でもお話しした通り、子どもの頃から救命を学ぶことの意義はいくつもあります。私も子どものころ、近所の大人から教わったことを40年経過した今も鮮明に記憶していますし、そうした人の優しさを今でも覚えています。情愛をもって接していただいたことに感謝をしています。
また、この救命教育は12年間継続してここまでやってきましたが、その秘訣は、関わる仲間同士が信じあい、協力しあったということだったと思います。そして、何よりも子どもたちの可能性を全員が信じてきたからだと思っています。
これまでの経験をいかして、これからは、教育と医療のプロが連携したより質の高いプログラムを通じて、子どもたちが考え、行動し、十分に表現できる学習の機会を提供していくものにしていきたいです。
そして、医療の立場から、情愛をもって子どもたちと共に学び考え、いつも社会が子どもたちに寄り添えるようなよりよい救命教育の環境を構築していければと思っています。








