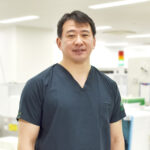「病院長を振り返って」 池田病院長
- 2025-4-3
- VOICE
この3月末、3年の任期を満了した池田病院長が退任しました。就任した2022年は、新型コロナウイルス感染症の影響もまだあり、職員のケアを含む病院機能の立て直しや強化が必要だった時期。それからの3年間を漢字一文字で表すと「交」だそうです。その人柄を知る人なら納得の一文字かもしれません。退任に際し、病院長としての日々を振り返ってもらいました。
それ行け!三重大学病院。それ行け!池田病院長。そのバトンと足跡が三重大学病院の次の歴史につながれ。
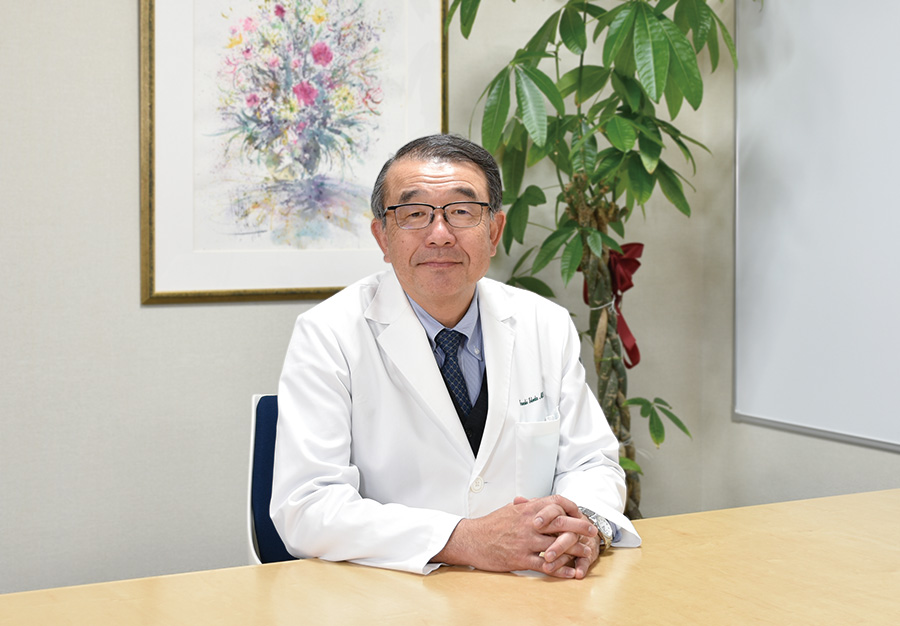
病院長を務めたこの3年間は、どのような日々でしたか。
院長に就任したときの私のミッションは、「麻酔科の再建」と「救急・ICUの充実」の二つでした。
三重大学病院では、麻酔科が2009年から二つの組織に分かれていたり、救命医療は救急医が少なく、各診療科からの応援医師によって継続しているという状況でした。
加えて、私の就任時には新型コロナウイルス感染症の第6波がピークを迎えていました。オミクロン株が主流となり重症化率は低下したものの、感染者の急増により院内クラスターの発生、職員の感染・休職が相次ぎ、対応に追われる日々が続きました。
しかし、職員の皆さんの協力により、これらの課題を乗り越え、さらにコロナ禍で低下した病院機能を回復させることができました。2023年度には当初のミッションを達成できたと感じています。
一方で、コロナ空床補償の補助金が終了した後、病院経営は非常に厳しい局面を迎え、2024年度は経営改善に全力を注ぎました。また、「総合がん治療センター」の設立や「みえブルーライン」バスの運行など、多くの成果をあげることができたと思います。
忙しい日々ではありましたが、非常に充実した3年間でした。
病院長就任には、「患者さんと職員の幸せファースト」ということもよく話されていましたね。
院内への取り組みとしては、「患者さんが幸せになるには、職員が幸せでなければならない」との信念で、その実現を目指してまず立ち上げたのが、「職員幸福度向上ワーキンググループ」です。
その一環として、院内保健室、サバティカル研修(職員旅行)、職員向け料理教室などの新たな行事を導入しました。
また、患者さんの利便性向上のために、先ほども触れた津駅と病院を直通で結ぶ「みえブルーライン」バスの運行や外来フロアへのコンシェルジュの配置を行いました。
患者サービスの向上と職員の働きやすさ、つまりは患者さんと職員の幸せファーストについては、こうした施策を中心に力を入れてきました。
医師として医療にあたった何十年と院長としての3年間、その大きな違いは何でしたか。
院長としてそれまでと最も大きく違ったことは、医学・医療の枠を超えて、多様な分野の方々と交流できたことです。
また、病院全体を管理する立場として、財務管理、安全対策、感染対策など、一専門領域の医師としてはあまり深く関わることのなかった分野について学び、判断するということもその一つでした。同時に、病院を運営する上で、診療だけでなく、これらの要素が不可欠であることも改めて実感しました。
その院長としての日々を「漢字一文字」で表すとすれば?
「交」です。
広範な分野の方々と交流できたことが、私にとって大きな財産となりました。その意味を込めて「交流」の「交」を選びました。
特に、三重県内の他の医療機関で活躍されている病院長の先生方をはじめ、多くの医療関係者と知り合えましたし、2023年6月には、鳥羽市で2日間にわたり「全国国立大学病院長会議」を主催し、全国の病院長や事務長の皆さまと貴重な意見交換を行うことができました。
また、三重県庁や津市などの自治体関係者、銀行の頭取、産業界の取締役など、医療以外の分野の方々とも関わる機会に恵まれました。
これらのつながりを今後も大切にし、交流を深めていきたいと思います。
そうした経験やつながりを院長退任後はどういかしていきますか。
2025年4月から済生会松阪総合病院に赴任することになりました。そこでは、病院の新築計画や松阪市民病院との合併が私の主なミッションになりそうです。
現在の地域医療構想では、病院の機能を明確にし、連携を強化しながら、「治す医療」から「治して支える医療」への転換が求められています。政府の求める地域医療構想に合致する形として、済生会松阪総合病院、済生会明和病院、松阪市民病院が連携し、それぞれの病院の職員の皆さんと協力しながら、急性期・回復期・慢性期・在宅医療まで一貫して対応できる体制の構築を目指していきたいと考えています。
また、「一人の医療者が三つの病院に勤めている」と言えるような、ダブル・トリプルアポイントメントの勤務形態を実現できるよう、これまでの経験をいかして尽力したいと思っています。
4月1日に佐久間新院長が就任しました。バトンタッチとしてのエールをお願いします。
現在、三重大学病院にとって最も重要な課題は病院経営です。特に高額薬剤や高額医療材料のコスト負担は大きく、大学病院全体に共通する構造的課題となっています。患者さんメリットを最大化しつつも、この課題に対してぜひ画期的な打開策を見出していただきたいと願っています。
また、佐久間先生のおかげで、三重大学病院は、「MUDX(Mie University Digital Transformation)」をベースとして、電子処方箋をはじめとする医療DX(デジタルトランスフォーメーション)において全国の大学病院の先頭を走っています。これを三重県全体に拡大し、より多くの医療機関と連携を深めていただきたいと思います。
最後に、今後の三重大学病院への期待についてもお聞かせください。
三重大学病院の職員の皆さんは、本当に素晴らしい方々ばかりです。診療の方向性がしっかり定まれば、その結束力は全国一だと確信しています。
ぜひ、職員の皆さんが幸せを感じながら働ける環境を整え、「医療人の育成」、「“最後の砦”となる診療」、「世界的な研究」、「医師の派遣」という四つの柱をさらに発展させ、三重県唯一の特定機能病院としての役割を果たし続けていただきたいと願っています。
医療スタッフや事務職員、外部委託のスタッフを含め、三重大学病院の日々の運営に携わるのは、総勢約2500人。表から、裏から様々な形で関わるその一人ひとりの力や想いが、平常通りの診療を支えています。
安全な診療、優れた診療、質の高い診療、いずれも技術や設備だけでは成し遂げられません。
VOICEのコーナーでは、いろいろなスタッフの声を通して、三重大学病院の診療に欠かせない「人」としての側面をお伝えします。